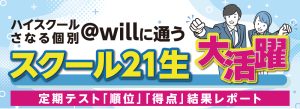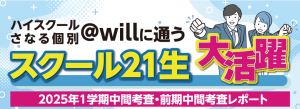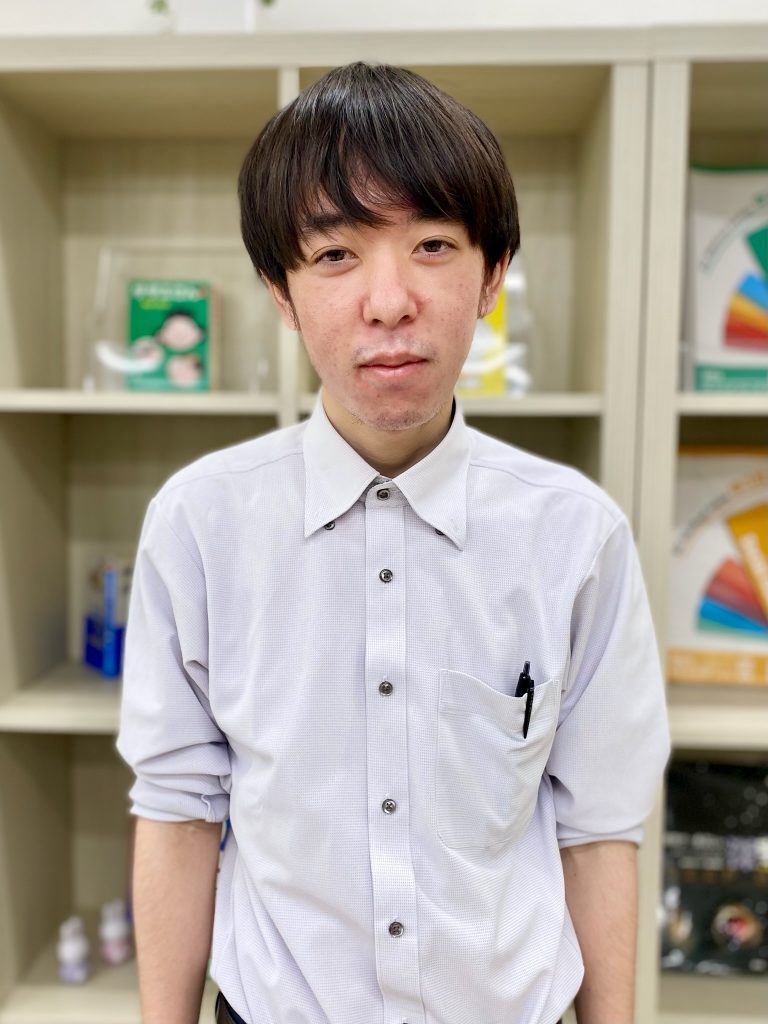〇今年の学習を振り返る3つのポイント
1. 成績の推移をチェックしよう
1学期から冬休み前までの定期テストや模試の結果を見返してみましょう。どの教科が伸びたか、どこに課題があるのかを把握することが、来年の学習計画に直結します。
2. 学習習慣の定着度を確認
毎日の勉強時間、家庭学習のリズムなど、自分の学習スタイルを振り返ることも大切です。
3. 目標に対する進捗を見直そう
志望校合格、定期テストの順位など、年の初めに立てた目標に対してどれだけ近づけたかを振返りしましょう。
〇まとめ
2025年が「良い年だった」と感じる人も、「思うようにいかなかった」と感じる人もいるでしょう。
大切なのは、1年をしっかりと振り返り、次にどう活かすかを考えることです。