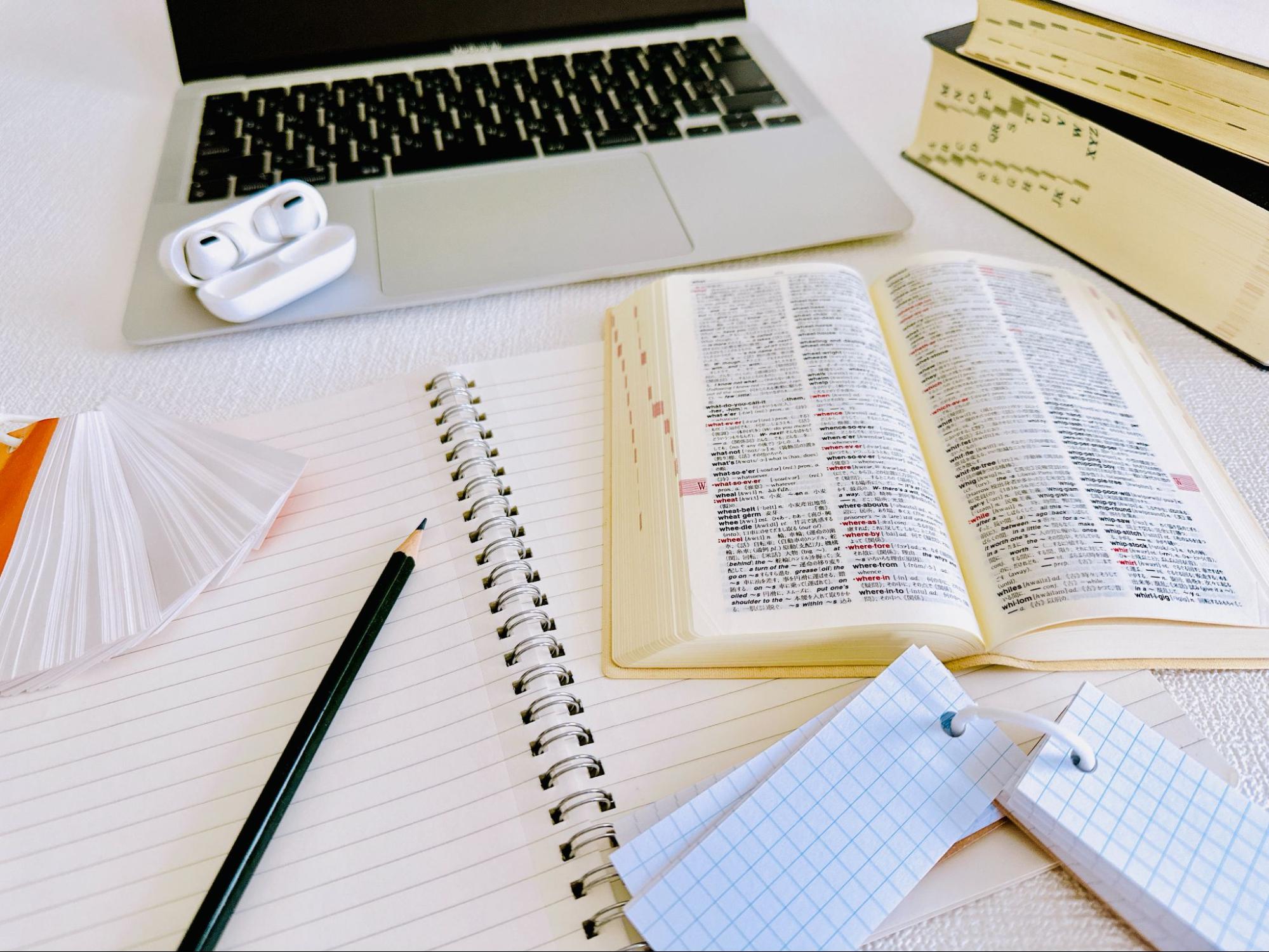受験勉強において、暗記は避けて通れません。しかし、ただやみくもに覚えようとしても効率が悪く、時間ばかりがかかってしまいます。
そこで本記事では、暗記が苦手な人でもスラスラ記憶できる効果的な暗記方法を7つ紹介します。
さらに、科目別に具体的な勉強法も詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
受験期に役立つ効果的な暗記方法

効果的な暗記方法を身につけることは、志望校との距離を縮めるために欠かせません。ここでは、暗記力を大幅に向上させる6つの方法を紹介します。
- 何度も繰り返して解く
- アウトプットを重視する
- 夜に覚えて朝に復習する
- 理解することに重点を置く
- 自主的にテストをして点数を記録する
- 家族や友人・人形に向かって講義する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 何度も繰り返して解く
暗記が苦手でも、問題を何度も繰り返し解くことで記憶は定着します。最初は答えを見ながらでも構わないので、同じ問題を最低でも3回は解くことが重要です。
1回目は、答えを確認しながら解き、2回目は半分程度自力で解けるようになり、3回目以降は徐々に正答率が上がっていくでしょう。
英単語なら同じ単語帳の同じページを毎日見る、数学の公式なら同じ問題を数日間あけて解くという方法が効果的です。
人間の脳は繰り返し触れた情報を重要であると判断し、長期記憶として定着させる仕組みが備わっています。
一度に完璧に覚えようとせず、60%程度の理解でも次に進み、後日また戻って解き直すサイクルで取り組みましょう。
繰り返し解くことは一見遠回りに見えますが、結果的に最も確実で時間効率のよい暗記方法です。
2. アウトプットを重視する
暗記したことを声に出したり書いたりする「アウトプット」を繰り返すことで、記憶が定着しやすくなります。
教科書を読むだけでなく、覚えた内容を何も見ずに紙に書き出す練習をしましょう。
問題集を解くことも重要なアウトプットで、間違えた問題は必ず見直して再度解き直します。覚えたつもりでも翌日にもう一度アウトプットして、記憶が残っているか確認することも大切です。
読んで覚えるより、手を動かして覚える方が脳に刻まれやすいため、アウトプットを中心とした暗記法を実践することが合格への近道となるでしょう。
3. 夜に覚えて朝に復習する
夜に暗記して朝に復習すると、記憶が定着しやすくなります。人間の脳は、睡眠中に情報を整理し、短期記憶から長期記憶へと移行させるはたらきがあるからです。
寝る前の1〜2時間に覚えたい内容を声に出して読んだり、書いたりして暗記しましょう。朝起きてすぐ、前夜に覚えた内容を5〜10分かけて見直すことで記憶の定着率が上がります。
たとえば、英単語なら夜に20個覚えて、朝に昨日の夜に覚えた単語の確認テストをするのがおすすめです。歴史の年号や化学式も同様で、夜に暗記した内容を次の日の朝にきちんと覚えているかチェックしましょう。
朝の復習時に思い出せなかった部分は、その日の夜にもう一度重点的に見直します。夜と朝に勉強することを習慣化すれば、暗記が苦手な人でも記憶力が向上するでしょう。
4. 理解することに重点を置く
暗記が苦手でも、内容を正しく理解することで記憶に残りやすくなります。丸暗記ではなく「なぜそうなるのか」を考えながら覚えることが重要です。
数学の公式なら、どのように導き出されたかを理解してから覚えることが大切です。英単語は、語源や成り立ちを知ることで、関連する単語も一緒に覚えられます。
理解を深めるには、自分の言葉で説明できるかを確認することが大切です。友達に教えるつもりで声に出して説明してみると、理解度がわかります。
図や表を自分で描いてみることも、頭のなかで内容を整理するのに役立つでしょう。
5. 自主的にテストをして点数を記録する
記憶を定着させるためには、自分でテストを作って解き、その点数を必ず記録するという勉強方法も効果的です。覚えたい内容から問題を作り、翌日・3日後・1週間後と繰り返し解いてみましょう。
たとえば、英単語なら日本語を見て英語を書くテストを20問作成します。解いたあとは必ず採点し、日付と点数をノートに記録しましょう。
点数が下がった箇所は重点的に復習し、満点になるまで繰り返します。記録を見返すと、どの分野が苦手か一目でわかるため、勉強計画も立てやすくなるでしょう。
間違えた問題には印をつけ、なぜ間違えたのかについてもかんたんにメモしておきます。テスト形式にすることで本番の緊張感に慣れ、実際の試験でも力を発揮しやすくなります。
継続的な自己テストと記録の積み重ねが、確実な暗記力向上への近道となるでしょう。
6. 家族や友人・人形に向かって講義する
自分が覚えた内容を、家族や友人あるいは人形などに向かって「講義」することは、記憶の定着に非常に効果的な方法です。
誰かに説明しようとすると、単に暗記しているだけではなく、内容を自分の言葉で整理し直す必要があります。
その過程で理解が深まり、あいまいだった部分や知識の抜けも自然に明らかになります。
また、聞き手が疑問を投げかけてくれたり、説明がうまく伝わらなかったときには、どこが理解不足なのかを客観的に確認できるでしょう。
たとえ相手が人形やぬいぐるみであっても、声に出して話すことで脳が活性化し、記憶に残りやすくなります。
覚えたことを説明する学習法は、知識を確実に自分のものにするための強力な勉強法です。
【教科別】受験勉強に取り入れたい実践的な暗記法

教科にあった暗記法を実践すれば、効率的に受験勉強を進められます。ここでは各教科に特化した実践的な暗記方法を5つ紹介します。
- 国語
- 社会
- 数学
- 理科
- 英語
それぞれの教科の特性に合わせた暗記法を詳しく見ていきましょう。
1. 国語
国語の暗記は、文章の構造を理解しながら重要語句を覚えることが大切です。
古文単語は、例文とセットで音読し、現代語訳と一緒に声に出して覚えましょう。
漢文の句法は、書き下し文を何回か書いて手で覚えることで定着しやすくなります。古典文法の活用表は、リズムをつけて唱えることで自然に覚えられるでしょう。
漢字は、部首の意味を理解し、似た漢字をグループ化して覚えるのもおすすめです。
このような方法を組み合わせれば、効率よく暗記できます。
2. 社会
社会科目の暗記は、できごとや人物を時代の流れと関連付けて覚えることが重要です。
年号を丸暗記するのではなく「なぜその出来事が起きたか」という因果関係を理解しながら覚えましょう。
たとえば「1868年明治維新」とだけ覚えるのではなく「黒船来航で開国を迫られ、幕府の権威が失墜したから倒幕運動が起きた」とストーリーで記憶します。
一方、地理は地形・気候・産業を関連付けて覚えることが大切です。
「瀬戸内海沿岸は雨が少ないから、水を多く使う稲作より果樹栽培が盛ん」のように理由とセットで暗記しましょう。地理の白地図に自分で情報を書き込むのも効果的です。
毎日10分でも継続的に復習することで、徐々に知識が定着していくでしょう。
3. 数学
数学の暗記は、公式の意味を理解しながら覚えることが重要です。
公式を丸暗記するのではなく、なぜその公式が成り立つのかを図やグラフで視覚的に理解しましょう。
たとえば、三角関数の公式は単位円を描いて角度と座標の関係から導き出せることを確認します。解法パターンは、問題を解きながら身につけるため、同じ種類の問題を3回以上繰り返し解きましょう。
1回目は、解答を見ながら手順を確認し、2回目は自力で解き、3回目で時間を計って解きます。
間違えた問題は、解法の流れを自分の言葉でノートに書き出すことも大切です。
数学の得点力を付けるには、理解と暗記のバランスを取りながらひたすら反復練習する必要があります。
4. 理科
理科の暗記は、図やイメージと結びつけることで記憶に残りやすくなります。具体的な学習方法の例は、以下のとおりです。
| 科目 | 学習方法 |
| 物理 | 公式を丸暗記するのではなく、実際の現象と結びつけて理解することが大切。 |
| 化学 | 元素記号を語呂合わせで覚え、化学反応式は反応前後の変化を矢印で表しながら理解する。 周期表は縦の列(族)の性質の共通点に注目すると覚えやすい。 |
| 生物 | 細胞の構造を自分で図に描き、各部位の名称とはたらきを友人や家族に説明しながら覚える。 |
また、実験の手順は「なぜその操作をするのか」の理由を理解し、意味とセットで覚えましょう。
理科の暗記は、ただ覚えるのではなく「なぜそうなるのか」を理解しながら進めることが、長期記憶につなげるコツです。
5. 英語
英語の暗記は、単語を文章やフレーズごとに覚えると、記憶に定着しやすくなります。
たとえば、単語帳で「abandon=捨てる」と覚えるより「abandon the plan(計画を断念する)」のように実際の使い方で覚えましょう。
単語は、品詞ごとにグループ化し、動詞なら過去形・過去分詞形もセットで覚えます。長文読解で出会った単語は、文脈とともにノートに記録するかマーカーで線を引いておき、あとで見返すと記憶に残りやすくなるでしょう。
また、リスニング教材の音声を真似して発音練習すると、音と意味が頭のなかで結びつきます。
このような勉強法を組み合わせることで、暗記が苦手でも英語力を着実に伸ばせるでしょう。
受験勉強の暗記はコツを押さえればできる!毎日コツコツ積み上げよう

今回紹介した暗記法を実践すれば、これまで覚えられなかった内容も効率よく覚えられます。
暗記が苦手だと感じていた人も、コツを押さえて毎日実践することで、目に見えて成果を感じられます。
受験本番まで限られた時間のなかで、効率的な暗記法を身につけて志望校合格を勝ち取りましょう。