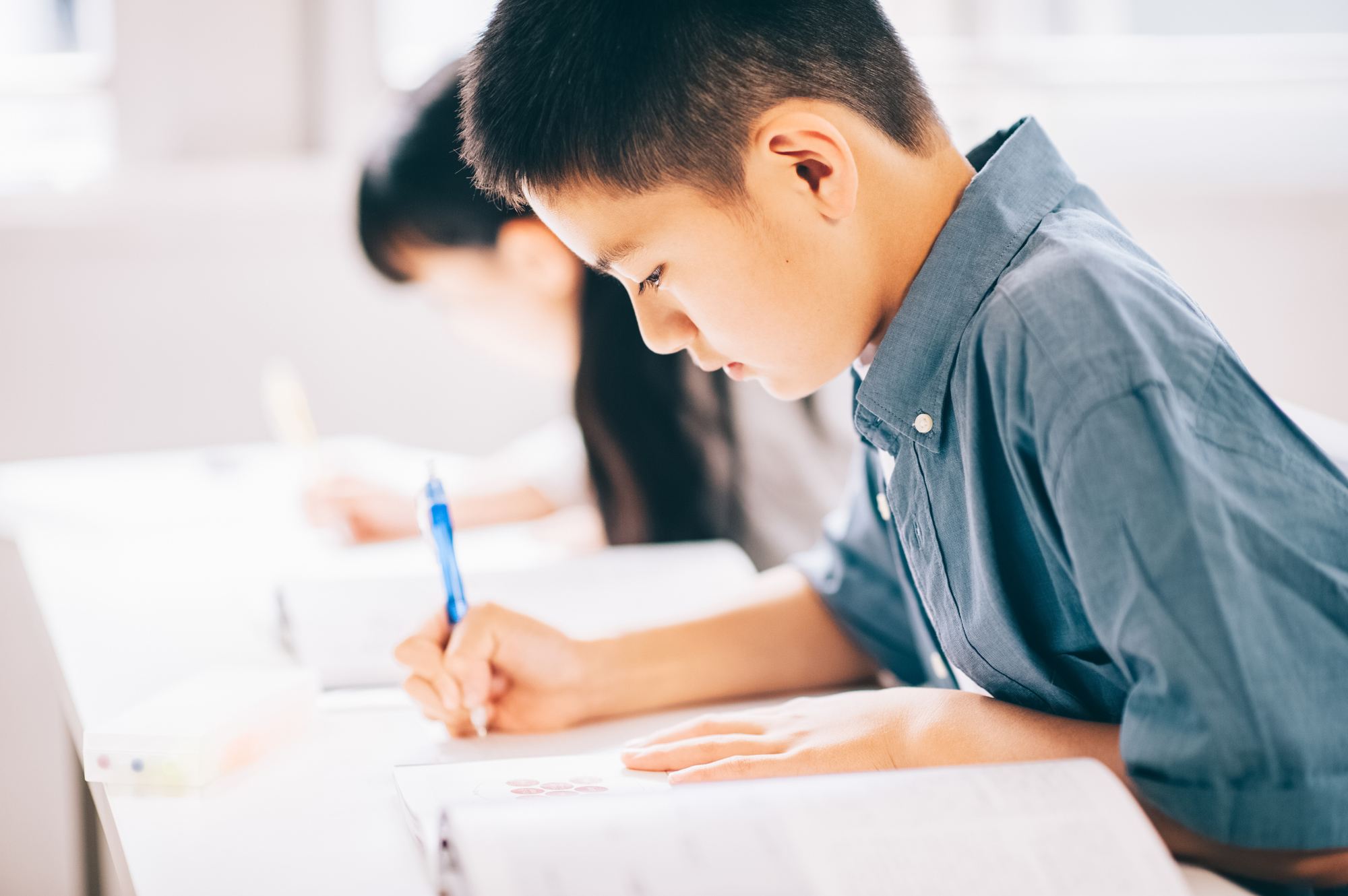夏期講習が終わり、いよいよ入試に向けて模試を毎月のように受験する時期に入りました。今回は、中学受験における模試の活用法についてお伝えします。
模試は「羅針盤」
まず押さえておきたいのは、模試は単なる「学力テスト」ではないということです。むしろ、入試本番に向けての戦略を組み立てるための 「羅針盤」 として活用すべきものです。
模試が返却されると、つい数字に一喜一憂しがちです。もちろん右肩上がりで成績が伸びれば理想的ですが、これまでの指導経験から見ても、それはむしろ稀なケースです。
親の受け止め方がカギ
好結果であれば素直にほめ、次の飛躍につなげることができます。重要なのは、そうではなかったときの対応です。
結果に親子で動揺しすぎるのは逆効果。親の不安は子どもに伝わり、やがて「親の顔色をうかがって勉強する」状態になりかねません。そうなると学習効果は大きく下がります。難しいことではありますが、模試の数字を冷静に受け止めることが、受験を成功に導く大切な姿勢です。
模試を「課題発見の材料」に
模試の本当の価値は、今後の学習にどうつなげるかにあります。
多くの模試では、科目別・設問ごとの正答率が公表されます。ここを丁寧に分析し、正答率が高い問題で誤答があれば必ず見直し、「解き直しノート」を作ることをおすすめします。
小さなつまずきをひとつずつ克服していくことが、最終的に合格への足がかりとなります。そして、分析結果は今後の学習計画や、併願校を含めた志望校選びにも役立てられるのです。
伴走者としての親の役割
以前の記事で親は「伴走者」とお伝えしました。模試の結果に左右されすぎず、冷静に見守りつつ、前向きな声かけを続けること。それが子どもが学習に前向きでいられる最大のサポートです。
数字は“絶対”ではない
最後に強調したいのは、模試の数字はあくまで目安にすぎないということです。合格可能性80%でも不合格はありえますし、30%でも合格をつかむことはあります。筆者自身、後者のケースで合格を勝ち取った生徒を多く見てきました。
次回は「過去問題」について取り上げます。実際の出題傾向との相性が合えば、模試の数字にかかわらず合格を手にできることも少なくありません。
模試を「結果」ではなく「未来へのヒント」として活かすこと。
その姿勢が、お子さんの可能性を大きく広げます。