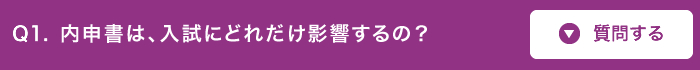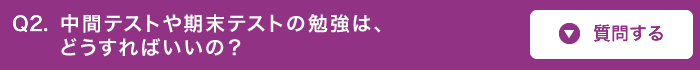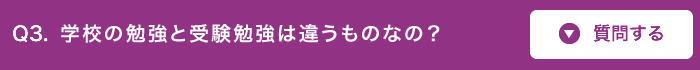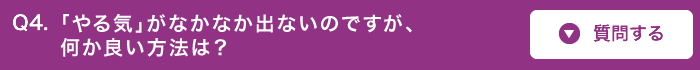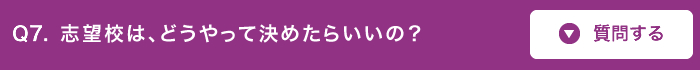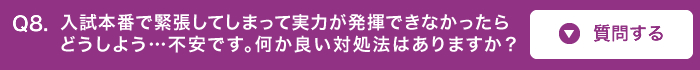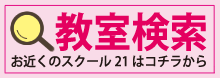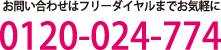スクール21動画
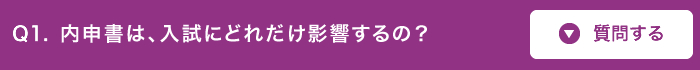
-
- A.埼玉県公立高校の入試制度は近年めまぐるしく変化し続けています。
数年前から学力検査の得点だけではなく、内申点も点数化されました。
ただし、この内申点というものが実際何点として扱われるか、高校によってかなり差があります。
ですから影響を及ぼすことは確かなのですが、その高校によってどの程度大きいか小さいかは変わってきます。
大事なのは目指す高校がどの程度内申点を重視するのか確認することです。スクール21入試情報センターはこれまでの経験・実績により各高校の内申点の配分を把握しています。
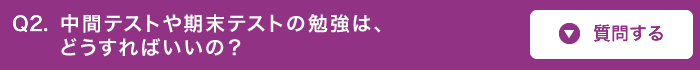
-
- A. 多くの生徒さんは中間テストや期末テストが始まる2週間か1週間前にテスト範囲をどのように復習しよう、何を覚えようと計画を立て、それに基づいてワークや問題を解ことをテスト対策の勉強だと認識していると思います。
もちろんそれは大切なことですが、最も重要なことを忘れたままではいけないといえます。
それは何かと言いますと、日々中学校で受けている一つひとつの授業内容をしっかりと身につけるということです。
中学校での授業に対する取り組みというものが、定期テスト対策の第一歩です。
それなくしていくら直前で詰め込み勉強をしても、効果がうすいと言わざるを得ません。
ですから日々の中学校での学習を充実させるとともに、そのまとめとして定期テストの対策をスケジュールし、計画することが大切です。
その一助として、スクール21各教室では通学する中学校の教科書に合わせた定期テスト対策授業を無料で行っています。
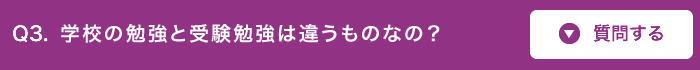
-
- A. これは難しい質問なのですが、受験をする高校によって必要な学習の内容や量というものが異なります。
ただ一般的には受験のための勉強というものと、学校での勉強が別々に並列して違うものとして存在しているわけではありません。
どのような受験勉強でも基本となるものは中学校の教科書であり、中学校での学習です。
それがベースになり、その上にどれだけ自分の受験に必要な学習内容を積み上げていくかが大切です。
ですから違うか同じかといえば、同じ部分が土台にありそしてそれに少し違う部分が上に積み重なっていくというイメージですから、学校によって対応の仕方は違うといえます。
スクール21各教室では進路相談を含めて目指す高校によってどのような勉強をしたらよいのかを指導します。
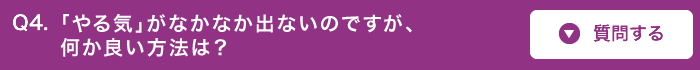
-
- A. やる気が出るかどうかというのは、環境による影響も無視できないのですが、ここでは、“自分でできる工夫”をひとつあげておきます。
それは、小さくても良いので身近な目標をたくさん、頻繁に設定するということです。立てた目標をクリアーしたら「○」をノートに書いていったりしてカウントすると良いでしょう。シールを用意しても良いです。
例えば、「今日は8時から勉強を始める」とか、学習に直接関係なくても、「明日は○時に起きる」とか、「入浴・身支度を40分で終える」とかでも良いでしょう。あるいは、「この1問を5分で解く」のように、問題単位で時間設定しても良いです。
“小さな身近な目標”は他にもたくさん考えられます。大切なことは、小さなことでもできたら○をつけていくということです。ノートを用意して、日付をかき、○を書いていきます。どんどん○がついていくとやる気も出てきます。このように、自分の行動を律する習慣が付いてくると、物事が計画的に進み、気持ちも上向きになることが多いようです。
受験で志望校に合格するこという大きな目標を達成するには、日々の小さな行動の積み重ねが欠かせません。

-
- A. 高校へ進学する際、「一番行きたい高校」を一般に第1志望と呼んでいます。「その学校以外なら高校に行かない!」というケースはほとんどないでしょう。
第1志望校以外の受験校を一般に「併願校」と呼んでいます。もし、第1志望の高校がダメだった場合の次の候補を考えておきます。また、いくつか受験したけどすべて不合格だった、ということでは困りますよね。従って、「確実に合格できるであろう安全校」も受験します。これも併願校と位置づけられます。
併願校を大きく分類すると、第1志望校に次ぐ志望校と、もしもの時のための安全校の2種類ということになります。

-
- A. 受験生が高校の様子を知るためのチャンネルはいくつもあります。代表的なものをあげると、
①受験生及び保護者を対象にした「学校説明会」
②受験生や保護者に向けた「公開授業」や「オープンスクール」
③「文化祭」や「体育祭」のうち一般公開されるもの
④そして「個別相談」です。
説明会や文化祭などは、広く全体に向けた“発信”になるのに対して、個別相談では、高校の先生と個別に相談できるというのが大きな特徴といえるでしょう。相談の内容は多岐にわたりますが、主なものをあげますと、次の3種類の相談が多いようです。
1)学校の様子や教育課程等で気になる点を質問したり、興味を持った点についてより
詳しく聞く。
2)受験に際して、個人的に不安な点を直に相談する。
3)今の成績で受験した場合、合格の可能性がどの程度なのかの相談。(この相談が私学のみ)
3)については良く勘違いをすることもありますので、詳しく説明します。
各私立高校において、10月から12月にかけて行われる「合格の可能性についての話し合い」。
■対象・・・受験生本人(または保護者)。
■場所・・・多くは、高校校舎。外部会場の場合もある。
■資料・・・会場テストの成績個票・通知票のコピーなど・検定等の合格証書
■相談内容・単願や併願での合格の可能性。(多くの高校で、出願基準や合格の目安を設けている。)
この種類の個別相談には重要な注意点があります。
◆実際の相談会では、合格の目安を直接受験生に公表する高校もあれば、数字は
全く教えない高校もあります。(出願基準は公表されます。)
◆成績の基準は,多くの受験情報誌に掲載されますが,一般的に公表されているのは「中学校の評定のみ」です。会場テストの成績基準や合格の目安は一般には公表されないケースがほとんどです。一般の受験生が知り得るのは個別相談会の場で,合格の可能性を個別に説明されるときにほぼ限定されます。
基準や目安を満たしている場合、相談会に参加した生徒は、入試の合否判定についてとても有利な扱いになります。どの程度有利になるかという度合いは高校によってまちまちですが、「ほぼ合格が約束されてしまう」高校も少なくありません。
県内私立の大部分および都内の一部の私立高校での“個別相談”では、その場で(会場テストその他の成績資料を基にして)合否の見通しが伝えられることが多いのですが、ここには多くの人が認識をしていない重要なことが潜んでいます。個別相談の場というのは、埼玉県受験生およびその保護者にとって半ば常識のようにとらえられ、とかく“確約”をもらえる高校の受験を優先する傾向にあるようです。
ただし、この流れには十分な注意が必要です。というのは、成績資料を基にした合否の見通しは、いわば口約束でしかなく、それは、正式な選考方法として明記されているわけではないということです。募集要項にも載っていません。そのため、曖昧な表現でやりとりされることが多く、そこには意味の取り違えや勘違いが発生することもまれではありません。具体的にはこんな感じです。
高校の先生:(成績を見て)『この成績であればまずに大丈夫です。しっかりと維持してくださいね。』
受験生 :『わかりました。』(確約がもらえたと考える)
実際にこのようなやりとりがされた後、安心して成績が下がってしまい、不合格となるケースもあります。また、その高校の過去問に真剣に取り組まないまま入試に臨むというのも危険なことです。受験生にとっても、高校にとっても、この“事前の個別相談による見通し”はメリットが大きいのですが、その仕組みへの過大な依存が、弱い受験生、手を抜いてしまう受験生、チャレンジを避け、確約をもらえる高校にだけ目を向ける受験生を増加させていることも事実です。
一方で、個別相談で良い返事をもらえたとしても、合格のために必要なことをしっかりと実行し、手を抜かない受験生、逆に厳しい話がされてもあきらめず努力する受験生も存在します。学力だけではなく、受験に向き合う意識も2極化しているということが表面化していないながらも大きな問題点としてあげられるわけです。
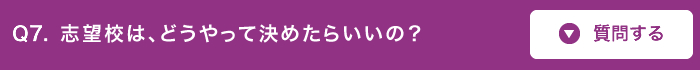
-
- A. おそらく多くの受験生の方が気になっているのは、高校の偏差値と自分の成績の比較、それと当然毎日通えるかといった地理的な条件で、それを踏まえて志望校を選んでいると思います。
しかし、それだけではなくぜひとも考慮に入れておきたいことがあります。
それは高校の3年間というものは、これからの長い人生を歩んでいく上でのひとつの通過点です。
ですから自分は大人になったらどんなふうになりたいのか、社会に出てからどんなことをしたいのか、そういうことを少しでもよいので考えてほしいのです。
そしてそれを実現するために高校や大学ではどのような勉強をしたいのか、さらにその勉強をすることのできる高校や大学はどこなのかを考え学校を選ぶことが大切です。
そうすればより深みのある選択ができると思います。
スクール21は埼玉県における長年の実績から各高校の内容や特徴を把握しています。
どんなことでもご相談ください。
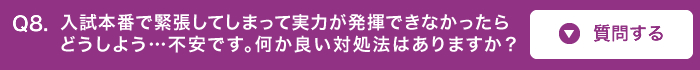
-
- A. 「こうすれば必ず実力を発揮できる」という万能の処方箋はありませんが、ひとつ多くの受験生に有効なポイントを伝授します。
入試の日は、起床の時間や家を出てからの交通等、普段と異なる行動をすることになります。
本番で実力が発揮できなくなる原因のひとつとして、「前の日によく眠れなかった」ということを良く聞きます。
『明日は入試だから早く起きなければ…。だから今日は早く寝よう』と思って早く床についてもなかなか寝付けなくて結局寝不足になってしまうようです。
これを回避するには、前の日だけではなく、できれば1週間前から起床、就寝の時間帯を入試本番の時間に合わせた生活をすることです。
「前日は22:00に就寝し、当日は5:00に起床する」予定であれば、1週間前から起床、就寝の時間をそれに合わせるということです。
はじめの2~3日はなかなかうまくいかないかもしれませんが、意識的に習慣化すればできるようになります。
さらに、このような「本番1週間前生活練習」を日頃の会場テストで練習してみると良いでしょう。
とにかく慣れていないことをするには、その予行演習を計画し、しっかり練習するようにするのがポイントです。
スクール21各教室では受験前の生活パターンも指導します。